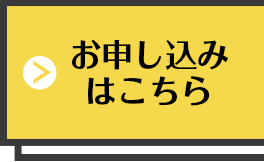不動産担保ローンは相続時に活用できる?利用事例とメリット・注意点を解説

相続が発生すると、相続税の納税や代償金、遺留分の支払いなどでまとまった資金が必要になることがあります。高額になることもあるため、手元の資金でまかなえない場合もあるでしょう。
所有する不動産を担保に融資を受ける「不動産担保ローン」は、原則として利用目的が問われないため、相続時にも活用できます。
本記事では、相続における不動産担保ローンの活用事例と、相続時に活用するメリットを解説します。注意点も踏まえ、不動産担保ローンの利用をご検討ください。
相続で不動産担保ローンを利用する事例
不動産担保ローンは、所有する不動産を担保に融資を受けるローン商品です。原則として利用目的に制限がないため、幅広い場面で活用できます。
相続が発生すると、相続税の支払いなどでまとまった資金が必要になることがあります。
手元の資金でまかなえない場合は、不動産担保ローンの利用も検討しましょう。
具体的には、以下のような場面で不動産担保ローンが活用できます。
- 相続税のお支払い
- 代償分割の代償金のお支払い
- 遺留分のお支払い
- 弁護士費用のお支払い
関連記事:不動産担保ローンとは?メリット・デメリットや利用する流れなどを解説
相続税のお支払い
相続が発生したとき、相続財産の価値が基礎控除額を超えると相続税の申告・納税が必要です※。相続税は、原則として現金で一度に納めることになっています。
また、相続税の申告・納税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
不動産のみを相続した場合や相続財産のほとんどが不動産の場合、限られた期間で納税のためのまとまった現金を用意できないケースもあるでしょう。
相続した不動産を売却して相続税の納税資金に充てる方法もありますが、納税期限が10ヶ月と決まっているため、価格交渉で不利になりやすく、相場よりも安く売却せざるを得ない場合があります。
また、なかなか買い手がつかない、あるいは相続人全員の同意が得られず売却できないなどの理由で、納税期限に間に合わないことも考えられます。
不動産担保ローンを利用すれば、比較的短い期間で相続税の納税資金を用意することが可能です。
※基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算した金額です。代償分割の代償金のお支払い
代償分割で遺産を分割する際にも、不動産担保ローンを活用できる可能性があります。
代償分割とは、1人または複数人の相続人が相続財産を現物で取得する代わりに、他の相続人に対して債務を負担する遺産分割の方法です。
相続財産が不動産のみ、または大半が不動産の場合、平等に分割するのは困難です。そこで、特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に相続分に見合った代償金を支払うことで遺産分割を行う「代償分割」が用いられます。
不動産を相続する際、相続人で共有して相続する方法もありますが、相続後に売却や利用方法などでトラブルになりやすい傾向があります。また、相続人全員が不動産の取得を希望しているとは限りません。
こうした場合にも代償分割が用いられますが、代償金が高額になり、資金を捻出するのが難しい場合もあるでしょう。不動産担保ローンを利用すれば、相続した不動産を担保に代償金に充てる資金を借入れすることも可能です。
遺留分のお支払い
遺留分とは、民法によって法定相続人(兄弟姉妹とその代襲者を除く)に保障された最低限の取り分です。
本来、遺産を誰にどれだけ相続させるかは自由に決めることができますが、遺された相続人の生活を保障するために一定の相続人には最低限の遺産相続を求める権利が認められています。
遺留分を有する相続人が遺留分に相当する財産を受け取れなかった場合、「遺留分侵害額の請求」を行えば遺留分を取り戻すことができます。
なお、遺留分侵害額の請求とは、遺贈を受けた者に対してその侵害額に相当する金銭の支払いを請求する手続きです。
遺留分侵害額を請求された側は、侵害額に相当する額を現金で支払わなければなりません。従来は、相続財産そのものを返す「現物返還」が原則とされていましたが、2019年7月1日の民法改正によって現金での支払いが原則となりました。
しかし、侵害額に相当するまとまった現金を用意するのが難しい場合もあるでしょう。こうした場面でも、不動産担保ローンの活用が検討できます。
弁護士費用のお支払い
相続トラブルを解決するための弁護士費用の支払いが負担になるケースもあるでしょう。
相続財産が不動産のみ、または大半が不動産だと、相続トラブルが起こりやすい傾向があります。不動産は平等に分割するのが難しく、相続人間で不公平が生じやすいためです。
裁判所によると、2023年の遺産分割事件数は13,872件であり、2000年(8,889件)と比べると約1.5倍増加しています。
トラブルが起きそうなときや起きたとき、弁護士に依頼すれば遺産分割がスムーズに進みやすくなる、または適切なアドバイスを受けることができますが、弁護士費用(相談料や着手金、報酬金など)が高額になるケースもあります。
不動産担保ローンは、原則として利用目的が自由であるため、相続トラブル時に発生した弁護士費用の支払いにも利用可能です。
相続時に不動産担保ローンを利用するメリット

不動産担保ローンを利用すると、相続に伴う支払いに対応できるだけでなく、遺産分割がスムーズに進みやすくなる可能性もあります。
相続時に不動産担保ローンを利用する主なメリットは、以下のとおりです。
- 無担保ローンと比べて金利が低め
- 高額・長期の借入れも可能
- 不動産を手放さなくてよい
無担保ローンと比べて金利が低め
不動産担保ローンで融資を受ける際は、不動産を担保として提供するため、無担保ローンと比べて金利が低い傾向があります。
そもそも担保とは、返済不能となった場合に備えて、あらかじめ債務の弁済に充てる手段として提供するものです。
利用者が返済できなくなると、金融機関は担保不動産を売却して融資金を回収します。無担保ローンと比べて金融機関側の貸し倒れリスクが低くなることから、比較的金利が低く設定されます。
その他の条件が同じ場合、金利が低いほど利息の額や総返済額を抑えることが可能です。
高額・長期の借入れも可能
無担保ローンと比べて融資額が大きく、長期にわたって返済できることもメリットのひとつです。
不動産を担保とする不動産担保ローンでは、申込者の返済能力や担保価値などから融資額が決定されます。不動産の担保価値によっては高額融資も可能なため、相続に伴って高額な資金が必要になった場合も対応できる可能性があります。
また、不動産担保ローンでは、比較的返済期間を長く設定できるため、ゆとりを持ったご返済が可能です。ただし、返済期間が長くなると総返済額が大きくなる点には注意が必要です。
不動産を手放さなくてよい
不動産担保ローンを利用すれば、不動産を手放すことなく相続時に必要な資金を用意できます。
相続に伴ってまとまった資金が必要な場合、相続した不動産を売却して納税資金などを確保する方法もありますが、売却すると不動産を手放さなければなりません。
また、住み続けたいと思っても、賠償金を支払えないために代償分割を諦め、やむを得ず換価分割(不動産を売却して分割する方法)を選ぶケースもあるでしょう。
不動産担保ローンを利用すれば、不動産を手放すことなく相続税の納税資金を調達できます。また、代償分割が行いやすくなり、遺産分割が円滑に進む可能性があります。
不動産担保ローンを利用する際のデメリット・注意点
不動産担保ローンは、相続時に発生するさまざまな資金ニーズにも対応できる可能性があります。ただし、以下のデメリット・注意点も踏まえて検討しましょう。
- 審査が実施される
- 諸費用・手数料がかかる
- 不動産に抵当権が設定される
審査が実施される
不動産担保ローンに申込むと、他のローンと同様に審査が実施されます。
不動産担保ローンの審査で評価されるのは、主に「申込者の返済能力」と「担保価値」の2つです。
担保価値が低いと、希望した金額をお借入れできない場合があります。また、不動産担保ローンに限らず、過去にローンを滞納したなどの理由で信用情報機関に金融事故の情報が登録されていると、ローンの審査に通過するのは難しいでしょう。
なお、不動産担保ローンでは担保価値の評価を行うため、無担保ローンと比べて審査にかかる時間が長い傾向があります。申込みの際は、余裕を持って手続きしましょう。
関連記事:不動産担保ローンの審査基準は? 落ちやすい人の特徴や通過のポイントを紹介!
諸費用・手数料がかかる
不動産担保ローンを利用する際、利息(借りたお金の対価として支払う金銭)とは別に諸費用・手数料がかかります。主な諸費用・手数料は以下のとおりです。
| 諸費用・手数料 | 概要 |
|---|---|
| 事務手数料 | 融資を受ける金融機関に支払う手数料 |
| 印紙税(実費) | 印紙税(実費) |
| 登記費用 | 抵当権設定登記に関する費用(登録免許税、司法書士報酬費用など) |
| 不動産調査料 | 担保となる不動産を調査するための手数料 |
| 火災保険料 | 火災保険の保険料 |
実際の諸費用・手数料は金融機関によって異なるため、事前に確認しましょう。
関連記事:不動産担保ローンにかかる手数料・諸費用は?シミュレーションも紹介
不動産に抵当権が設定される
不動産担保ローンで融資を受ける際、担保不動産に抵当権が設定されます。
抵当権とは、債務者が返済不能となった場合に優先的に弁済を受けられる権利のことです。万が一返済ができなくなると、金融機関によって担保不動産が売却され、その売却代金から融資金が回収されます。つまり、返済ができなくなると、不動産を失うことになります。
不動産担保ローンを利用する際は、金融機関が提供している返済シミュレーションを活用し、無理のない返済計画を立てることが重要です。
AGビジネスサポートの「不動産担保ローン」は事業資金のご融資が可能
AGビジネスサポートでは、法人・個人事業主さまを対象とした「不動産担保ローン」をご提供しています。
相続した不動産を事業目的で利用する場合は、相続税の納税資金や代償金をお借入れいただける可能性があります。ただし、いわゆるお勤めの方にはお申込みいただけません。
AGビジネスサポートの「不動産担保ビジネスローン」なら、最高5億円までご融資が可能です。また、最高5,000万円(個人事業主は2,000万円まで)までご融資が可能な「不動産担保カードローン」もご用意しています。
簡易診断の結果は最短1日でお知らせでき、最短3日でご融資が可能です。スムーズなお借入れを希望する事業者さまもぜひご検討ください。
詳細を理解したうえで相続時に不動産担保ローンを利用しよう
不動産担保ローンは、原則として利用目的が決まっていないため、相続税や代償分割の代償金、遺留分のお支払いなどに幅広く利用できます。
不動産を担保にするため、無担保ローンと比べて金利が低い傾向があり、審査によっては高額・長期の借入れも可能です。
いっぽうで、希望した金額を借入れできるとは限らない点や、ご返済が滞ると不動産を失うリスクがある点には注意が必要です。
相続時に不動産担保ローンを利用すれば、まとまった資金を用意できるだけでなく、遺産分割が円滑に進みやすくなる可能性もあります。メリット・デメリットを理解したうえで不動産担保ローンの利用を検討しましょう。
おすすめ記事
-

-
- 監修者
- 竹下 昌成(たけした あきなり)
-
- プロフィール
- 大家業、TAC講師、竹下FP事務所代表。1971年生まれ。兵庫県西宮市在住。立教大学卒業後、地銀やノンバンク、住宅メーカーFPを経て現職。30歳から大家業をスタート、45歳でFIRE。年間家賃収入3,600万円。得意分野は住宅購入と不動産投資。
- 資格情報
- CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザーほか
- https://mbp-japan.com/hyogo/fp-takeshita/