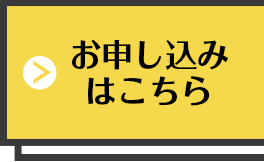不動産投資の税金対策とは?法人・個人事業主が不動産で節税可能な仕組みを解説

不動産投資が税金対策につながると聞いたことはあっても、詳しい仕組みが分からない方もいるのではないでしょうか。
本記事では、不動産投資が税金対策となる仕組みや注意点などを解説します。
法人による不動産投資とは?
法人による不動産投資とは、不動産投資の事業運営を個人でなく法人で行うことを意味します。不動産投資の事業内容は法人でも個人でも変わりません。
不動産投資を目的に副業として設立した法人は、資産管理会社(いわゆるプライベートカンパニー)と呼ばれることもあります。
不動産投資を法人化する流れと個人所有との違い
不動産投資の法人化には、一般的な会社設立と同じ手続きが必要です。株式会社や合同会社など法人の種類によって、法人の種類や資本金の額、出資者の数などの設立条件を検討していきます。
- 個人が資本金を出して法人を設立
- 金融機関からの借入金により法人が物件を買い取り、法人名義に変更
- 不動産投資を法人の事業として運営
法人化にあたって、個人の管理する不動産を法人が買い取り、個人から法人へ名義変更する必要がある点に注意しましょう。
不動産の運営者が個人から法人へ変わると、かつての所有者である個人は法人の出資者として役員に就任します。そして、これまで得てきた賃料収入に代わり、会社から役員報酬や配当を受取ります。
| 個人による運用 | 法人による運用 | |
|---|---|---|
| 不動産の所有権 | 個人 | 法人 |
| 不動産投資による所得 | 貸収入や売却益 | 役員報酬や配当 |
| 課税される税金 | 所得税・住民税・譲渡所得税 | 法人税 |
表のとおり、個人による不動産投資と法人化には、所得の種類と課される税金の種類に大きな違いがあります。
不動産投資の法人化による税金対策の仕組み
不動産投資の法人化による税金の仕組みを具体的に紹介します。
個人の所得税より課税率を抑えられる
不動産投資で収入があったとき、法人と個人では課される税金の種類と税率が異なります。
個人には所得税と住民税、法人には法人税が課税されます。個人の所得税率は所得が増えるほど税率が高くなる累進課税で、5%から最大で45%に達します。
いっぽう、法人税は基本税率が23.2%で、法人住民税や事業税を合わせても実効税率は約34%(利益800万円超の中小法人)です。
所得税の税率(所得税のほか10%の住民税がかかります)
| 課税所得金額 区分 | 税率 |
|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% |
| 40,000,000円 以上40,000,000円 以上 | 45% |
法人税の実効税率
| 事業開始年度 | 中小法人 | 中小法人以外の法人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 課税所得金額 区分 | ||||
| 400万円以下 | 400万円~ 800万円以下 | 800万円超 | ||
| ~2025年3月31日 | 21.37% | 23.17% | 33.58% | 29.74% |
| 2025年4月1日~ | 25.84% | 27.55% | ||
出典:日本貿易機構(JETRO)「3.3 法人所得課税の概要(法人税・法人住民税・事業税)」
個人に課される所得税率は、900万円を越えた時点から法人税の実効税率の上限とほぼ変わりません。法人税の実効税率は一律のため、一定の所得を超えると、同じ所得でも法人化したほうが税率を抑えられます。
経費計上できる費目が多く課税所得を抑えられる
個人事業主も事業にかかる費用を経費計上できますが、不動産投資を法人化すると、経費計上できる費目が増えます。
法人になると本人や家族への報酬(給与や退職金)、出張費などの手当、法人を契約者とする生命保険料のほか、個人と同様に以下のような費目も経費になります。
・法人でも経費計上できる費目
借入金利息、火災保険料、管理費(管理委託料)、固定資産税、広告宣伝費、減価償却費、司法書士や税理士への報酬など
経費を正しく計上すればそれだけ課税所得を圧縮でき、税金対策につながります。
減価償却費を調整できる
不動産は建物の構造ごとに決まった耐用年数(使用に耐える年数)のあいだ、取得費用を減価償却費として経費計上できます。
たとえば、鉄筋コンクリート造マンションの耐用年数は47年のため、このマンションの取得費用は47年にわたって分割して経費に算入することが可能です。
法人全体で「損益通算」できる
損益通算とは、不動産所得・事業所得・山林所得の4つの所得区分で、同じ年度の利益と損失を相殺するもので、個人の所得税に適用される制度です。
法人にはこの損益通算の概念がありません。利益(益金)や損失(損金)はすべて「法人全体の損益」となり、別事業の赤字も不動産の売却益もまとめて相殺されます。
そのため、事業が黒字化しても、不動産で売却益が出ても、法人としての課税所得を抑えられる可能性があります。
さらに、個人の損益通算は損失(赤字)の繰越期間が最大3年であるのに対し、法人の欠損金(赤字)は繰越期間が最大10年です。長期の繰越期間も法人化による税金対策のひとつとなるでしょう。
相続税を抑えられる
個人で不動産投資をはじめる方のなかには、相続税対策と考える方がいます。
不動産を相続すると不動産評価額に応じた相続税を納めなければなりませんが、現金に比べると税額を低く抑えられる可能性が高く、税金対策しながら資産を残しやすいためです。
不動産所得を分散できる
先ほどの資産の分散は、法人税だけではなく、所得税の軽減にもつながります。
法人化によって、不動産投資で受取る所得は役員報酬に変わります。
- 役員1人で役員報酬1,000万円受取る:所得税率は33%
- 役員4人で役員報酬250万円ずつ受取る:所得税率は10%ずつ
さらに、役員報酬は税法上の給与所得に該当するため、給与所得控除が適用されます。
| 役員報酬(給与)の金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 55万円 |
| 1,625,001円~1,800,000円まで | 収入金額×40%-10万円 |
| 1,800,001円~3,600,000円まで | 収入金額×30%+8万円 |
| 3,600,001円~6,600,000円まで | 収入金額×20%+44万円 |
| 6,600,001円~8,500,000円まで | 収入金額×10%+110万円 |
| 8,500,001円以上 | 195万円 |
不動産投資の法人化で注意しておきたい点

税金対策として有効とされる不動産投資の法人化ですが、法人化するにあたって注意しておきたい点もあります。
法人の設立にコストがかかる
個人事業主として事業をはじめるのにとくにお金はかかりませんが、法人を設立するには30万円ほどのコストがかかります。
法人設立にかかる主な費用
| 定款費用 | 会社のルールや方向性をまとめた定款の作成費用 | 認証手数料、謄本代、収入印紙、印鑑証明書など |
|---|---|---|
| 登記費用 | 株式会社を設立する場合の登記費用 | 登記費用、登録免許税、会社実印登録費用 |
| 資本金 | 法人成りするための資本金 | 株式会社・合同会社は1円~ |
設立後の決算書作成など、ほかに手続きを依頼する場合、司法書士や税理士への報酬も必要です。また、社会保険に加入する場合は、社会保険料(労使折半)も発生します。
また、法人として新たに不動産を購入するなら、物件代金や仲介手数料に加えて、不動産取得税・登録免許税・消費税・印紙税などもかかるでしょう。
経営が赤字でも税金がかかる
不動産投資を法人化すると、事業所の所在地のある都道府県や市町村に対する、法人住民税の「法人税割」と「均等割」の納税義務を生じます。法人税割の税額は課税所得、均等割の税額は会社の資本金や従業員数に応じて決まります。
個人住民税は、赤字であれば、「所得割」も「均等割」も課税対象から外れる可能性があります。しかし、法人住民税の均等割は赤字であっても申告・納税しなければなりません。
法人住民税の均等割の税額は、資本金1,000万円以下かつ従業員50人以下の会社で、都道府県均等割2万円と市町村均等割5万円、計7万円からとなっています。つまり、利益が出ていない年度でも、1年で最低7万円の税金がかかります。
不動産の所有年数によっては売却益にかかる税金が高い
不動産投資の出口戦略としてゆくゆくは売却を検討している場合、物件の譲渡益にかかる税金も考慮するべきでしょう。
個人で所有する不動産の場合、所有期間によって譲渡益にかかる税率が変わります。物件の取得から5年までは約39%、5年を超えると約20%と、長く保有すると税率が大きく下がります。
しかし、法人の場合、不動産の譲渡益に関する所有年数による税率の違いはなく、法人税の税率は一律です。
| 個人 | 法人 | |
|---|---|---|
|
不動産の 所有期間 |
短期譲渡:所有期間5年以下 長期譲渡:所有期間5年超 |
所有期間の区分はない |
| 譲渡益にかかる税率 |
短期譲渡:39% 長期譲渡:20%※ |
法人税の実効税率 (約26~34%) |
そのため、5年以上所有する不動産を売却する場合、個人よりも法人のほうが高い税率を課されます。
※平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。法人の利益を個人が自由に使うことはできない
不動産投資の法人化で税金対策を実現しても、法人で得た利益は個人が自由に使えません。
個人が事業で得た利益は個人の収入ですが、法人として出した利益は会社の資産です。法人化しただけで、これまで変わらず不動産を運用していると代表取締役でも会社のお金は自由に使えないため、会社の資産と個人の資産を明確に分ける必要があります。
会社のお金を生活費などに流用すると、業務上横領罪などの罪に問われる恐れもあるため、じゅうぶん注意しましょう。
不動産投資の法人化で税金対策を考えるタイミング
不動産投資の法人化は、誰にとっても必ず税金対策になるとは限りません。不動産投資を続けるうえで、法人化を検討すべきタイミングはいくつかあります。
- 個人の課税所得が900万円を超えた
- 経費計上したい費目が多い
- 不動産投資の事業拡大を考えている
個人に課される所得税の税率は、課税所得900万円をさかいに23%から33%へ上がります。さらに住民税10%が加わる、利益800万円超の会社の法人税は実効税率約34%であると考えると、課税所得900万円は法人化の目安となるでしょう。
また、不動産投資の事業拡大を考えたときも、法人化を検討するタイミングです。法人化すると金融機関からの信頼を得られる傾向があり、事業拡大に向けた資金調達しやすいでしょう。
不動産投資の法人化の資金調達にはAGビジネスサポート
法人化に向けた不動産投資の事業拡大を検討しているなら、AGビジネスサポートの「不動産投資ローン」をご検討ください。
投資物件購入を目的とした資金をご融資するサービスで、法人だけではなく個人事業主も対象としているので、これから法人化をめざす方にも適しています。
融資金額は100万円から5億円までと幅広く、事業規模に合わせた資金の準備できます。また、 簡易診断最短1日、ご融資まで最短3日と、経営判断に合わせた対応が可能です※。
※申込時間帯によっては対応できない場合があります。※本審査の結果、ご希望に添えない場合もございます。
※法人契約の場合は原則代表者の連帯保証が必要です。また、担保提供者の連帯保証が必要な場合があります。
不動産投資の税金対策には正しい知識を身につけることが大切
本記事では、不動産投資の税金対策の仕組みや注意点などを詳しく解説しました。
課税所得が900万円を超えているのであれば、法人税の税率ほうが個人の所得税・住民税より低くなり、節税につながります。ほかにも、減価償却を柔軟に調整できる、経費計上の自由度が高い、相続税対策が強化されるなどもメリットがあります。
ただし、法人立ち上げには初期費用や決算などのランニングコストがかかるなど、法人化する際にはいくつか注意が必要です。
不動産投資の事業を拡大したいなら、資金調達の手段としてAGビジネスサポート「不動産投資ローン」をご検討ください。法人はもちろん、個人事業主にも対応するため、これから事業拡大や法人化をめざす方にもご利用いただけます。
おすすめ記事
-

-
- 監修者
- 竹下 昌成
-
- プロフィール
- 大家業、TAC講師、竹下FP事務所代表。1971年生まれ。兵庫県西宮市在住。立教大学卒業後、地銀やノンバンク、住宅メーカーFPを経て現職。30歳から大家業をスタート、45歳でFIRE。年間家賃収入3,600万円。得意分野は住宅購入と不動産投資。
- 資格情報
- CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザーほか
- https://mbp-japan.com/hyogo/fp-takeshita/