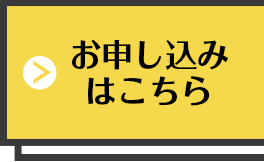不動産担保ローンにかかる手数料・諸費用は?シミュレーションも紹介

不動産担保ローンで借入れする際、利息のほかに事務手数料、印紙税、登記費用、保証料などの手数料・諸費用がかかります。
事務手数料や保証料のように金融機関によって金額が大きく異なる費用もあるため、申込みの前にしっかり確認することが重要です。
本記事では、不動産担保ローンで発生する手数料・諸費用を借入時・返済時に分けて解説します。不動産担保ローンを選ぶときのポイントも紹介するので、不動産担保ローンの利用を検討している方はぜひご覧ください。なお、多くの場合、保証料は金利に含まれているため本記事では触れていません。
不動産担保ローンの借入れで発生する手数料・諸費用
不動産担保ローンでお借入れする際に発生する主な手数料・諸費用は、以下のとおりです。
- 事務手数料
- 印紙税
- 登記費用
- 利息
- 火災保険料
- 不動産調査料
事務手数料
事務(取扱)手数料とは、不動産担保ローンを提供する金融機関に支払う手数料です。
多くの場合、借入金額に対する一定割合を支払いますが、定率ではなく定額で決まっている場合もあり、金融機関によって異なります。
定率の場合、借入金額が大きくなるほど事務手数料の負担も大きくなります。相場は、借入金額に対して0.0%~3.0%程度です。
印紙税
印紙税は、契約書や領収書など、印紙税法で定められた文書を作成する際に課される税金です。印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼付して納付します。
不動産担保ローンで借入れする際、金融機関との間で「金銭消費貸借契約」を締結します。金銭消費貸借契約は、印紙税法で定められた課税文書にあたるため、印紙税の納付が必要です。印紙税額は、借入金額に応じて決まっています。
| 借入金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円超50万円以下 | 400円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 |
登記費用
不動産担保ローンで借入れする際、抵当権の設定に関する登記費用がかかります。
不動産担保ローンは、不動産を担保に借入れする仕組みです。借入れする際、金融機関が担保となる不動産に抵当権を設定します
抵当権とは、債務者(ローン利用者)が返済できなくなったときに優先的に弁済を受けられる権利です。万が一不動産担保ローンの返済ができなくなると、金融機関が担保不動産を競売(強制的に売却する手続き)にかけ、売却代金から貸付金を回収します。
抵当権設定登記にかかる費用は、以下の2つです。
- 登録免許税
- 司法書士報酬費用
登録免許税は、登記をする際にかかる税金のことで、以下の式で税額を算出できます。
いっぽう、司法書士報酬費用の金額は、依頼する司法書士によって異なります。相場は30,000円~50,000円程度です。
利息
不動産担保ローンに限らず、借入れをしたときは金利に応じた利息が発生します。利息とは、借主が貸主に使用料として支払うお金です。
不動産を担保に借入れする不動産担保ローンは、無担保ローンと比べて貸し倒れリスクが低いため、一般的に無担保ローンよりも金利が低めです。ただし、実際に適用される金利は審査で決まるため、申込者によって異なります。
なお、多くの場合、保証料は金利に含まれています。保証料とは、保証会社に支払う手数料です。不動産担保ローンは、原則として保証人なしで利用できる代わりに、保証会社の保証が必要となる場合があります。
火災保険料
建物を担保にする場合は、基本的に火災保険へ加入する必要があります。火災保険に加入していないと、万一火災などで損害を受けた際に返済ができなくなるリスクがあるためです。
火災保険の保険料は、物件の種別や補償内容によって異なります。
また、火災保険への質権設定を求められる場合もあります。質権を設定することで、火災などで不動産が消滅してしまった際、金融機関が保険金から貸付金を回収できる仕組みです。
不動産調査料
金融機関によっては、担保となる不動産を調査するための調査料(鑑定料)がかかる場合があります。
定額の場合と、「借入金額×○%」と定率で決まっている場合があるため、事前に確認しましょう。
不動産担保ローンの返済で発生する手数料・諸費用

次に、不動産担保ローンを返済する際に発生する手数料・諸費用を解説します。
- 中途解約手数料
- 条件変更手数料
- 抵当権抹消費用
中途解約手数料
不動産担保ローンでは、返済期日前に一部または全部を繰上返済する場合、中途解約手数料がかかる可能性があります。「中途完済手数料」「早期返済違約金」「期日前返済手数料」など、名称は金融機関によってさまざまです。
多くの場合、返済元金に対して一定割合の中途解約手数料がかかります。返済元金が多いほど、中途解約手数料も高くなる仕組みです。
なお、事業者ではない個人向けの不動産担保ローンの場合、一般的に中途解約手数料はかかりません。ただし、繰上返済手数料がかかる場合があります。
条件変更手数料
借入期間中に返済金額や返済期間などの融資条件を変更する際、条件変更手数料がかかる場合があります。
一般的に定額で設定されていますが、金融機関によって異なる場合があるため事前に確認しましょう。
抵当権抹消費用
不動産担保ローンをご完済しても、担保不動産に設定されていた抵当権は自動的に抹消されません。そのため、不動産担保ローンを完済したあとは抵当権抹消に関する手続きが必要です。
抵当権抹消にかかる登録免許税額は、不動産1個につき1,000円です。つまり、土地と建物の場合の税額は2,000円となります。また、司法書士に依頼する場合は、別途司法書士報酬費用が必要です。
不動産担保ローンでかかる手数料のシミュレーション
不動産担保ローンで借入れする際にかかる手数料・諸費用のシミュレーションを紹介します。手数料・諸費用を以下の条件と仮定し、借入額500万円、1,000万円の2つのケースを試算しました。
- 事務手数料:3.0%
- 保証料:なし
- 登録免許税:0.4%
- 司法書士報酬:50,000円
借入額500万円の場合
借入額500万円の場合、手数料・諸費用の額は以下のとおりです。
| 手数料・諸費用 | 金額 |
|---|---|
| 事務手数料 | 150,000円(500万円×3.0%) |
| 印紙税 | 2,000円 |
| 登録免許税 | 20,000円(500万円×0.4%) |
| 司法書士報酬 | 50,000円 |
| 合計 | 222,000円 |
借入額1,000万円の場合
いっぽう、借入額が1,000万円の場合の手数料・諸費用は、以下のとおりです。
| 手数料・諸費用 | 金額 |
|---|---|
| 事務手数料 | 300,000円(1,000万円×3.0%) |
| 印紙税 | 10,000円 |
| 登録免許税 | 40,000円(1,000万円×0.4%) |
| 司法書士報酬 | 50,000円 |
| 合計 | 400,000円 |
上記のように、借入金額が大きければ数十万円の費用がかかります。
いっぽう、借入金額が少額になるほど手数料・諸費用が占める割合が高くなる点に注意が必要です。
不動産担保ローンを選ぶときのポイント
不動産担保ローンを選ぶ際に知っておきたい、手数料や費用に関するポイントや注意点を解説します。
- 金利を比較する
- 手数料・諸費用も考慮して選ぶ
- 違法業者に注意する
法人や個人事業主の取引量が増えるなか、ローン商品を提供する会社や金融機関も増加していますが、ローン商品を選ぶときには、手数料のほか、企業としての信頼性などもよく検討してから決めることが重要です。
また、事業者の返済能力や信用情報などにより、借入れできない可能性がある点は理解しておきましょう。
金利を比較する
なるべく金利が低い不動産担保ローンを選ぶことで、利息負担を抑えられます。
不動産担保ローンは、比較的高額の借入れも可能なローン商品です。借入金額が大きくなるほど、金利が低いローンを選んだときの利息負担の軽減効果も大きくなります。
不動産担保ローンの金利タイプは、変動金利と固定金利の2つです。一般的に、変動金利は、固定金利と比べて金利が低く設定されています。ただし、借入期間中に金利が変わる場合があります。
不動産担保ローンを選ぶ際は、上限金利や金利タイプをよく確認しましょう。
手数料・諸費用も考慮して選ぶ
不動産担保ローンを選ぶ際は、金利だけでなく、手数料・諸費用も考慮しましょう。
不動産担保ローンで借入れする際、事務手数料や印紙税、登記費用などの手数料・諸費用がかかります。金利が低くても、手数料・諸費用が高ければ負担が大きくなります。
特に、事務手数料や調査料は金融機関によって大きく異なるため、しっかり確認しましょう。また、借入れの際の費用だけでなく、中途解約手数料や条件変更手数料も確認しておくことが大切です。
なお、貸金業法では、実質年率を表示するよう定めています。実質年率とは、利息だけでなく事務手数料なども含めた合計額を年率で換算したものです。不動産担保ローンの金利をみる際は、実質年率を確認しましょう。
違法業者に注意する
貸付をする際は、財務局長または都道府県知事の登録を受けなければなりません。しかし、貸金業登録を受けない、または登録を受けていながら法外な高金利で貸付するヤミ金業者には注意が必要です。
不動産担保ローンを選ぶ際は、貸金業登録番号が正しいか、金利が法律の上限を超えていないか確認しましょう。法律による上限金利は、以下のとおりです※。
| 借入金額 | 上限金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20.0% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18.0% |
| 100万円以上 | 年15.0% |
不動産担保ローンは、所有する土地や建物などの不動産を担保にして融資を受ける有担保ローンです。不動産担保ローンで自宅を担保とする場合、返済が不能になると自宅が売却されるリスクがあります。
リスクを理解したうえで、その資金調達がそもそも必要なのかを検討し、提供先や社会に役立つ事業成長に向けて、信頼できる方に話す、専門家や機関などの相談窓口を選ぶことが重要です。
緊急性を伴う融資を必要としている、事業で迅速な成長を目指している場合は、現実的な返済計画を立てたうえで不動産担保ローンの利用を検討しましょう。
※参考:日本貸金業協会「5 お借入れの上限金利は、年15%~20%です」事業者向けの不動産担保ローンのご相談は「AGビジネスサポート」へ
AGビジネスサポートでは、事業者向けの不動産担保ローンを提供しています。
不動産担保ビジネスローンの事務手数料率は、0.00%~3.00%です。お申込みの際は、印紙代(実費)、登記費用(実費)の手数料が発生します。
AGビジネスサポートなら、簡易診断最短1日、ご融資まで最短3日です。手数料や諸費用について不安がある方はお電話でもお問合せいただけます。ぜひご相談ください。
まとめ
不動産担保ローンで借入れする際、初期費用として事務手数料や印紙税、登記費用などがかかります。
借入金額によっては、数十万円の費用が必要です。また、借入金額が少額だと費用の割合が高くなるため、負担に感じる場合もあるでしょう。
手数料や諸費用が負担にならないよう、申込みの前に確認しておくことが重要です。また、不動産担保ローンを選ぶ際は、金利だけでなく手数料・諸費用も踏まえて選びましょう。
おすすめ記事
-

-
- 監修者
- 竹下 昌成(たけした あきなり)
-
- プロフィール
- 大家業、TAC講師、竹下FP事務所代表。1971年生まれ。兵庫県西宮市在住。立教大学卒業後、地銀やノンバンク、住宅メーカーFPを経て現職。30歳から大家業をスタート、45歳でFIRE。年間家賃収入3,600万円。得意分野は住宅購入と不動産投資。
- 資格情報
- CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザーほか
- https://mbp-japan.com/hyogo/fp-takeshita/