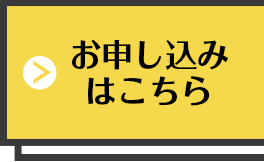不動産担保ローンの借入可能額の目安は?決まり方や計算方法をわかりやすく解説

不動産担保ローンの借入可能額がいくらくらいになるのか、お申込み前に目安を知りたいと考える方は多いでしょう。借入可能額はさまざまな要素から決定されますが、担保となる不動産の評価額によって大きく左右されます。
評価額を知るには、不動産の価値を正しく知ることが必要です。
この記事では、不動産担保ローンの借入可能額の目安や決まり方、不動産評価額から導き出す計算方法などを詳しく解説します。
不動産担保ローンの借入可能額の目安
不動産担保ローンの借入可能額の目安は、担保となる不動産の評価額によって異なります。契約者がローンの返済を続けられなくなれば、金融機関は担保不動産を売却して現金化し、残債を回収しなくてはいけません。そのため、融資した金額を回収できるかどうかを、不動産評価額によって判断しています。
ただし、不動産の評価額がそのまま借入可能額とされるのではなく、事業の利益(収入)、借入希望額や返済期間、他社からの借入状況なども影響する点も忘れてはいけません。
不動産の評価額といっても、一律に定められた計算方法はありません。そのため、金融機関ごとに不動産の評価に対する考え方や評価方法が異なり、一般には開示されていません。
そこで、不動産担保ローンの借入可能額の目安を知るため、担保掛目を利用します。担保掛目とは借入金に対する担保価値、つまり借入可能額の割合を示すものです。
担保掛目についても情報開示はされていませんが、おおむね60~80%とされています。
たとえば不動産評価額が3,000万円なら借入可能額は1,800万円~2,400万円程度と予測できます。
不動産担保ローンの借入可能額の決まり方
不動産担保ローンの借入可能額は、担保となる不動産の評価額からおおよその目安をつけられます。しかし実際の金融機関への申込みでは、不動産の評価額に加え、申込者の返済能力を中心にさまざまな要素を審査したうえで判断されます。
事前にどのようなポイントを審査されるのか把握しておくと、いざ申込みをするときにも不安は少ないでしょう。
次に、不動産担保ローンの借入可能額を決める考え方や審査基準を紹介します。
「担保となる不動産の評価額」が借入可能額を左右する
担保となる不動産の評価額も、不動産担保ローンの借入可能額を決定づける要素のひとつです。不動産の担保価値が高ければ高いほど高額の融資を受けやすくなり、反対に、担保としての価値がないと判断されると審査に通らない恐れもあります。
ただし、不動産の評価基準や評価額の計算方法は金融機関により異なるため、同じ不動産でも金融機関ごとに評価額は変わります。
期待するような借入可能額を提示してもらえなかった場合には、別の金融機関の不動産担保ローンに申込むのもひとつの方法です。
評価額が低くなる不動産の特徴①形状・状態・立地に問題がある
形状や状態、立地に問題がある不動産は、売却までに時間がかかることがあります。返済が滞ったときに現金化しにくくなるため、担保価値も低くなる傾向があります。
また、建物がある土地にも注意が必要です。築年数が古く、管理状態に問題がある物件は評価額が低くなりがちです。
評価額が低くなる不動産の特徴②利用制限がある
既存不適格建築物や借地権付き建物、再建築不可物件、市街化調整区域にある物件などは、建替の際に制限を受けることがあります。自由に活用できない分、評価額が低くなる傾向があるでしょう。
また、共同名義の不動産も注意が必要です。名義人1人のみの同意では処分ができないため、利用が制限され、担保としての評価額が低くなる傾向があります。
評価額が低くなる不動産の特徴③すでに抵当権が設定されている
すでに抵当権が設定されている不動産も、評価額が低くなる傾向にあります。抵当権を設定した順に弁済を優先的に受けられるため、二番抵当や三番抵当になる可能性がある不動産は敬遠されることがあります。
「申込者の返済能力」も借入可能額の判断材料になる
不動産担保ローンを扱う金融機関にとっては、申込者が融資したお金を滞りなく返済できるのかどうか、つまり「申込者の返済能力」が、借入可能額を決める重要なポイントになります。返済能力は次のポイントから総合的に判断されることが一般的です。
- 他社からの借入状況
- 信用情報
- 完済時の年齢
- 事業内容・継続年数
各ポイントを解説します。
他社からの借入状況
他社からすでに多額を借入れている状態で新たに借入れると、返済が滞る可能性が想定されます。そのため、不動産担保ローンに限らず、ローンに申込んだときは、他社からの借入額や借入件数、月々の返済金額などがチェックされることが一般的です。
すでに高額を借入れている場合や、担保となる不動産をほかのローンの担保として設定している場合は、借入可能額が低くなることもあります。
信用情報
他社からの借入状況に加え、信用情報もチェックされます。
返済が滞っている場合や返済に遅れたことがある場合、返済できずに債務整理をしたことがある場合などは、信用情報に何らかのトラブルとして記録されているかもしれません。借入可能額が低く設定されたり、借入れそのものが難しくなったりすることもあるでしょう。
完済時の年齢
定年退職後は収入が減る方も多いです。返済に充てられる金額も少なくなる傾向があるため、金融機関によっては完済時の年齢も考慮されるでしょう。
年齢に不安がある場合は、月々の返済金額を増やして返済期間を短縮する方法も検討できます。また、返済期間が短くなることで利息を減らしやすくなるというメリットもあります。
事業内容・継続年数
個人事業主や法人が借りる場合には、事業の安定性がチェックされることがあります。事業の安定性は、事業内容や継続年数などから総合的に判断することが一般的です。継続年数が短くても、ニーズが高く、将来性も期待できる事業内容なら、高く評価されることもあるでしょう。
いっぽう、事業者ではない個人の場合は、勤続年数が審査項目のひとつとなることもあります。勤続年数が長い方は収入が安定していると考えられるため、借入可能額が高くなる傾向があります。
借入可能額を決める不動産評価額の算出方法

不動産担保ローンで借入可能額を決める重要な要素、担保となる不動産の評価額がわかれば、担保掛目を乗じることで借入可能額の目安がわかります。不動産評価額がはっきりしない場合には、基本的な算出方法から概算を求めておくといざというときに便利です。
算出の前提として、不動産が更地であれば土地のみが評価され、土地の上に建物があれば土地と建物の評価を合算します。
それでは、土地と建物、それぞれの評価額を算出する方法を解説します。
土地の評価額を求める方法
土地の評価額を求める方法には、過去の不動産取引における価格を示す実勢価格や国土交通省が発表する公示地価などを含め、主に6種類の基準価格が挙げられます。
ただし、それぞれの基準価格には主な利用目的が決まっており、不動産担保ローンでの担保価値を知りたい場合には、公的機関の公表する公示地価・基準地価・路線価を参考にするのが一般的です。
| 公示地価 | 国土交通省が発表する1㎡あたりの標準価格(全国23,000ヵ所の標準地) |
|---|---|
| 基準地価 | 都道府県が発表する1㎡あたりの土地評価額 |
| 路線価 | 国税庁が発表する道路に面した1㎡あたりの評価額 |
上記の基準価格をもとに、該当する土地の面積を乗じて評価額を求めます。
建物の評価額を求める方法
建物の評価額は再調達価格をもとに算出するのが一般的で、これを「原価法」と呼びます。再調達価格とは現在と同じ建物を新築するのにかかる費用で、そこから経過年数による価値の消耗分を差し引いて計算します。原価法の計算式は以下のとおりです。
● 評価額=(1㎡当たりの単価×面積)×残存年数(耐用年数-築年数)÷耐用年数
建物は材質や工法などにより法定耐用年数が決められており、たとえば木造だと22年、鉄筋コンクリート造だと47年です。新築から年数を経るごとに評価額は下がり、法定耐用年数を超えると評価額はゼロになります。
ただし、保有する物件が賃貸用のマンションやアパートの場合、収益物件として「収益還元法」で算出します。収益還元法の計算式も確認しておきましょう。
● 評価額=1年の利益(賃料収入-必要経費)÷還元利回り
収益還元法の還元利回りは、周辺の類似物件の利回りを参考にするとよいでしょう。また、自用・賃貸用にかかわらず、複数の評価方法で総合的に評価することもあります。
不動産担保ローンの融資までの流れ
担保とする予定の不動産の評価額の目安がついており、不動産担保ローンへの申込みを検討中なら、申込みから融資までの流れをあらかじめ確認しておきましょう。金融機関によって、必要書類や諸費用の有無、融資までにかかる期間などに違いがあります。
ここではAGビジネスサポートの「不動産担保ビジネスローン」および「不動産担保カードローン」を参考に、流れを紹介します。
- 問合せ(調査):不動産の評価額を調査し、利用限度額の目安を回答
- 申込み:正式なお申込みに伴い、審査に必要な書類を提出
- 審査
- 契約:(根)抵当権設定契約と金銭消費貸借契約を実施して契約
- 融資:ご契約後はすぐに融資が可能
事前問合せは電話またはWEBからできるため、不動産の評価額や借入可能額に対する不安は申込み前に解消できます。
ただし、一般的な不動産担保ローンの手続きは申込み後にまず仮審査があり、仮審査を通過すると本審査、本審査を経て契約、融資に至ります。手順が多い分、融資実行までに1ヶ月程度の時間を要することも珍しくありません。
AGビジネスサポートなら最短1日で借入可能額を確認可能
不動産担保ローンでどれだけの金額を借入れできるのかわからず、事業計画を立てにくい、ローンの申込みがためらわれる、そのような方にはAGビジネスサポートの「不動産担保ビジネスローン」(貸付条件はこちら)および「不動産担保カードローン」(貸付条件はこちら)がおすすめです。
いずれも最短1日での簡易診断を利用できます。ご自身で複雑なリサーチや計算せずとも、不動産の評価額や借入可能額の目安などがわかる便利なサービスです※1。
借入可能額は「不動産担保ビジネスローン」で最大5億円、「不動産担保カードローン」で最大5,000万(個人事業主は2,000万円以下)となっており、用途に合わせてローンの種類を選べます。
また、お申込みからご融資までは最短3日となっており、一般的な不動産担保ローンと比べると短期間で資金を準備できる可能性が高いでしょう。時勢に合わせてテンポよく経営判断をされたい事業者さまにおすすめです。
※1法人契約の場合は原則代表者の連帯保証が必要。担保提供者の連帯保証が必要な場合があります。
不動産担保ローンの借入可能額に関するよくある質問
不動産担保ローンの借入可能額についてのよくある質問とその答えをまとめました。ぜひ疑問解消にお役立てください。
Q.借入可能額が低いときにはどうすればよい?
不動産の評価や借入額の算定は金融機関によって異なります。必要額を借りられないときは、別の金融機関に相談するのもひとつの方法です。
一般的に、銀行よりも消費者金融のほうが審査は柔軟とされています。銀行の不動産担保ローンで期待するような借入可能額を提示されなかったときは、消費者金融の不動産担保ローンも検討してみましょう。
Q.借入額によって諸費用は変わる?
金融機関によっては、事務手数料や抵当権設定登記の費用(登録免許税)などがかかることもあります。たとえば、事務手数料が借入額によって決まる(例:借入額の2.0%)場合なら、多額を借りると諸費用も高額になる点に注意が必要です。
まとめ
不動産担保ローンの借入可能額は、申込者の返済能力や担保となる不動産の評価額などによって決められます。
とくに不動産の担保価値は、万が一ローンの返済が難しくなったときに金融機関が残債を回収できるかどうかの判断要素であり、担保価値がそのまま借入可能額になる場合もあります。担保価値は不動産評価額の60~80%(担保掛目)とされるのが一般的ですので、まずはご自身の不動産評価額を正しく把握しておきましょう。
ただし、土地や建物の評価法はリサーチや計算が複雑です。またせっかく計算しても、金融機関によって評価法が異なるため、数字が一致するとは限りません。
そこでおすすめしたいのがAGビジネスサポートの「不動産担保ビジネスローン」および「不動産担保カードローン」で利用できる簡易診断です。最短1日で不動産の評価や借入可能額の目安がわかるので、ぜひご活用ください※。
※法人契約の場合は原則代表者の連帯保証が必要。担保提供者の連帯保証が必要な場合があります。
おすすめ記事
-

-
- 監修者
- 竹下 昌成
-
- プロフィール
- プロフィール:大家業、TAC講師、竹下FP事務所代表。1971年生まれ。兵庫県西宮市在住。立教大学卒業後、地銀やノンバンク、住宅メーカーFPを経て現職。30歳から大家業をスタート、45歳でFIRE。年間家賃収入3,600万円。得意分野は住宅購入と不動産投資。
- 資格情報
- CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザーほか
- https://mbp-japan.com/hyogo/fp-takeshita/