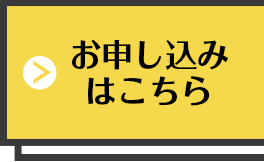ファクタリングで二重譲渡はNG!バレる理由や発覚したときのリスクを解説

ファクタリングを利用する際は二重譲渡に注意が必要です。二重譲渡が発覚した場合、刑事罰に問われる可能性があるほか、事業の継続が難しくなります。
二重譲渡は必ずバレるため、ファクタリング利用時は二重譲渡にならないように細心の注意を払う必要があります。
また、「そもそも二重譲渡ってなに?」という方もいると思います。
本記事では、ファクタリングの二重譲渡の概要やバレる理由、発覚したときのリスクなどを解説します。
ファクタリングとは
ファクタリングとは、事業者が保有している売掛債権(売掛金)をファクタリング会社が一定の手数料を徴収して買取るサービスで、法的には債権の譲渡契約になります。
本来、売掛金は期日を迎えてから現金化できるため、手元に現金を入手するまで時間がかかりますが、ファクタリングを利用すれば期日前に現金化が可能です。
そのため、資金調達手段のひとつとして利用されています。また、ファクタリングを活用し、期日前に現金化することで債権未回収のリスクも軽減できます。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違い
ファクタリングには2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあります。
2社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社間で取引を実施するファクタリングです。
2社間ファクタリングでは、先に売掛金の売却代金をファクタリング会社が支払い、利用者は売掛先から回収した売掛金をファクタリング会社へ支払います。
いっぽう、3社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社に加えて売掛先が取引に関わるファクタリングです。
売掛金の売却代金を支払うまでの流れは2社間ファクタリングと同じですが、3社間ファクタリングでは、ファクタリング会社が売掛先から直接売掛金を回収します。
ファクタリングでの二重譲渡とは
二重譲渡とは、同一のものを複数者に譲渡することです。ファクタリングでは、同一の売掛金を複数社に譲渡することを指します。
ファクタリングでの二重譲渡は、基本的に2社間ファクタリングで生じることがほとんどです。というのも、2社間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社間の同意があれば契約となるからです。
3社間ファクタリングでは売掛先の同意を得ることが必須となるため、二重譲渡が生じるのは稀なケースです。
どこが権利を有しているかの問題が生じるのを防ぐため、ファクタリング会社はしっかりと確認しているからです。
もし二重譲渡が発覚し、ファクタリング会社が売掛金を回収できない場合は、損害賠償を請求されるなどのリスクがあります。
ファクタリングで二重譲渡がバレる理由
ファクタリングの二重譲渡はバレるため、絶対にやめましょう。以下では、ファクタリングの二重譲渡がバレる理由を紹介します。
債権譲渡登記の情報照会による発覚
2社間ファクタリングでは、債権譲渡登記を必要とする場合があります。債権譲渡登記とは、企業が金銭債権を譲渡する際、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
債権を譲ったことおよび、譲り受けたことを公的に証明する手続きで、誰が権利を保持しているかが明確になります。
ファクタリング会社によっては、二重譲渡を防止するために債権譲渡登記を条件としている場合があります。債権譲渡登記は開示請求ができるため、登録後に二重譲渡をした場合、審査の段階でバレてしまいます。
ファクタリング会社への支払時による発覚
2社間ファクタリングでは、利用者が売掛金を回収後にファクタリング会社へ支払います。二重譲渡している場合、利用者が回収できる売掛金はひとつなのに対して、2社以上のファクタリング会社への支払いが生じます。
この際、資金がなければ支払いができないため、その時点で二重譲渡が発覚する可能性が高くなります。
ファクタリングでの二重譲渡が発覚したときのリスク

ファクタリングを利用時に二重譲渡が発覚すると、さまざまなリスクが生じます。以下では、二重譲渡が発覚した場合の主なリスクを紹介します。
横領罪や詐欺罪などの犯罪行為に該当する可能性がある
ファクタリングでの二重譲渡は、横領罪や詐欺罪などに該当する可能性があります。横領罪や詐欺罪は刑事罰の対象となるため、最悪の場合、懲役刑が課せられることがあります。
- 横領罪:5年または10年(業務上の横領)の懲役
- 詐欺罪:10年以下の懲役
横領罪や詐欺罪が適用されると社会的な信用も失われるため、二重譲渡は絶対にやめましょう。
取引先からの信用が失われる可能性がある
2社間ファクタリングでは、債権譲渡登記の確認がなければ、原則、売掛先にファクタリングの事実が知られることはありません。
ただし、二重譲渡によって、本来ファクタリング会社へ支払う売掛金が支払えない場合、ファクタリング会社から売掛先へ債権者が変更になった旨の通知が行われます。
売掛先にとっては身に覚えのない通知となるため、不信感を抱く可能性があるほか、売掛先にファクタリングの事実とともに不当なファクタリング利用も知られるため、その後の取引に悪影響を与える可能性があります。
損害賠償により事業の継続が困難になる
二重譲渡で刑事罰に問われない場合でも、ファクタリング会社から賠償請求が行われる可能性が高いです。
賠償請求では、本来ファクタリング会社に支払う金額に加えて、遅延損害金やそのほかの費用などを請求されるため、負担額が大幅に増えます。賠償金を支払えるほどの資金力がない場合、事業の継続も困難になるでしょう。
ファクタリングで二重譲渡に該当しないケース
ファクタリングの利用時は二重譲渡に注意が必要ですが、複数のファクタリング会社を利用しても二重譲渡にならないケースがあります。
以下では、ファクタリングで二重譲渡に該当しない主なケースを紹介します。
異なる売掛金を複数のファクタリング会社に譲渡する場合
同じ売掛金を使って複数のファクタリング会社と契約するのは二重譲渡となりますが、異なる売掛金を別々のファクタリング会社へ譲渡するのは全く問題ありません。
たとえば、A社とB社からの売掛金を保持している場合、A社の売掛金を1社目のファクタリング会社、B社の売掛金を2社目のファクタリング会社へ譲渡することは可能です。
ただし、故意でなくても同じ売掛金を使って複数のファクタリング会社と契約すると、二重譲渡に該当するため注意が必要です。複数のファクタリング会社を利用する際は、しっかりと売掛金の管理を行いましょう。
複数のファクタリング会社で相見積もりする場合
ファクタリング利用時は複数のファクタリング会社で見積もりを取り、各社の条件や手数料などを比較することが一般的です。
そのため、ひとつの売掛金を譲渡する場合でも、複数のファクタリング会社で見積もりを依頼するのは問題ありません。
ただし、複数社で見積もりを依頼し、そのまま複数社に申込んでしまうと二重譲渡となるため注意しましょう。
資金調達のご相談はAGビジネスサポートへ
AGビジネスサポートの「売掛債権ファクタリング」は、請求書1枚からご来店不要でお申込み可能です。
2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの両方に対応しており、2社間ファクタリングであれば最短即日の現金化も可能です。
買取手数料は「2%~※」となります。独自の審査を実施するため、売掛債権があれば赤字経営、債務超過、銀行リスケ中などでも買取りを検討します。
ファクタリングの利用を検討している方は、AGビジネスサポートへご相談ください。
※取引形態、買取金額によって条件が異なります。詳しくは営業担当にお問合せください。
ファクタリングを利用する際は二重譲渡に注意しよう
ファクタリングは売掛金の譲渡契約となり、同じ売掛金を使って複数のファクタリング会社に申込んでしまうと二重譲渡になります。
二重譲渡は横領罪や詐欺罪に該当する可能性があり、横領罪や詐欺罪は刑事罰の対象です。また、刑事罰に問われない場合でも、ファクタリング会社から賠償金を請求されるなどのリスクがあるため、絶対にやめましょう。
なお、異なる売掛金を別々のファクタリング会社へ譲渡する場合や、相見積もりを取る場合は二重譲渡に該当しません。
特に、相見積もりを取ってファクタリング会社を比較することは大切なことのため、二重譲渡に注意しながら最適なファクタリング会社を選びましょう。
AGビジネスサポートでは「売掛債権ファクタリング」を取扱っています。最短即日の現金化に対応しており、赤字営業や債務超過の場合でも買取りを検討します。
事業資金の調達に悩んでいる方は、AGビジネスサポートへご相談ください。
おすすめ記事
-

-
- 監修者
- 竹下 昌成(たけした あきなり)
-
- プロフィール
- 大家業、TAC講師、竹下FP事務所代表。1971年生まれ。兵庫県西宮市在住。立教大学卒業後、地銀やノンバンク、住宅メーカーFPを経て現職。30歳から大家業をスタート、45歳でFIRE。年間家賃収入3,600万円。得意分野は住宅購入と不動産投資。
- 資格情報
- CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザーほか
- https://mbp-japan.com/hyogo/fp-takeshita/